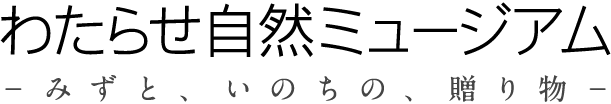コウノトリ ファンクラブ / ラムサール条約湿地「渡良瀬遊水地」
お知らせ
-
2022.03.01
-
2021.11.29
-
2021.11.11
-
2021.10.20
-
2021.10.04
※中止※第34回ヤナギ・セイタカアワダチソウ除去作戦の実施について(実施日:令和3年9月11日(土曜日)→令和3年10月9日(土曜日))
イベント
-
- 募集中
コウノトリ野生復帰
【2025年】コウノトリ「ひかる」・「レイ」ペアから誕生したヒナの愛称決選投票を行います。 ▲決選投票チラシ 小山市では…
-
コウノトリ「歌」(J0181・メス2歳)のはく製について(令和3年1月21日)
新型コロナウイルス感染拡大に伴う国の緊急事態宣言が栃木県に発出されたことを受け、渡良瀬遊水地コウノトリ交流館は1月15日…
-
コウノトリ野生復帰
概要 平成24年7月3日にラムサール条約湿地に登録された渡良瀬遊水地は、本州以南最大の湿地・ヨシ原を誇り、絶滅危惧種183種…
コウノトリ オリジナル アイテム
このサイトについて
「わたらせ自然ミュージアム」は、ラムサール条約湿地「渡良瀬遊水地」に棲むコウノトリのファンクラブサイトとして、栃木市、小山市、野木町はじめ周辺自治体の取組、イベント情報を発信するため、渡良瀬遊水地コウノトリ定着推進協議会(事務局:小山市 総合政策部 自然共生課)により運営されています。
| 運営 | 小山市役所 総合政策部 ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒-323-8686 栃木県小山市中央町1-1-1 小山市役所 総合政策部 ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課 |
| 連絡先 | 電話:0285-22-9288 |